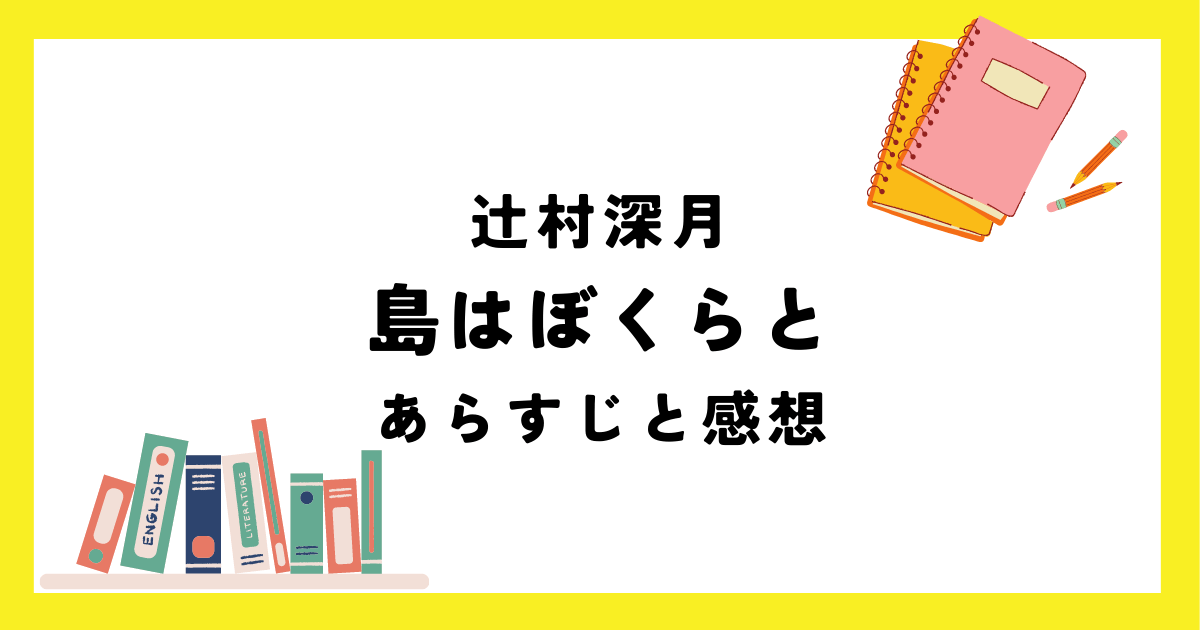あらすじ
これは「故郷」と「希望的な未来」の物語。
舞台は瀬戸内海に浮かぶ冴島。
島に暮らす高校2年生の朱里たちはフェリーで本土の高校に通っている。
子どもたちは、大学進学をきっかけに島を出て行くことがしきたりだ。
島の母親たちは、子どもが早く巣立つことを前提に育児をする。
出産前から丁寧に書き綴られた母子手帳を子どもたちは島を出る時に渡される。
島を出るもの、出ないもの。
新しく島にやってくるIターンやUターンの存在。
それぞれの価値観を大切に彼らは共存している。
いつまでも一緒にいられるわけではないということを常に感じているからこそ、冴島の住民が集まる空間は儚くも愛おしいのだろう。
朱里とその同級生、4人の視点で友情や恋、村人としての覚悟などが描かれている。
出会った時から別れを覚悟し共に暮らしてきた4人の別れはもうじき。
どんな表情で「行ってらっしゃい」、「行ってきます」とその日を迎えるのだろうか。
感想
主人公が高校2年生の少年少女ということだけで侮ってはいけない。
わたしも読む前は、淡い青春物語なのだろうとたかを括っていた。
しかし、読んだ後に気持ちの良い裏切りがあなたを包むでしょう。
朱里を始めた島の子どもたちは田舎臭いどころか島を通して世の中の縮図を早くも理解しているかのように大人びたところがあり、お互いの価値観を否定せず認め合う寛容さと穏やかさを感じる。
一方で、この小説のすごいところは「島に住む人の生活」のほかに、「リアルな村の現状」が描かれている。
今流行りの素敵な田舎暮らしを謳わず、地域産業の大変さや島の住民とIターンとの確執、医者の不在など生々しい問題が、より冴島を現実にある島へと変貌させる。
生きているとものごとは移ろい、たとえ同じ人間関係の中でも一緒のことはなく、変化していく。
そう知っているはずなのに、蔑ろにしてまな学ぶことの繰り返しかもしれない。
冴島の住民はそれを念頭に生活しているから、大切な人と過ごす時間が濃密で時にうるさく感じることもあるけれど、離れていても結びつきの強さを見せつける。
この物語をもっと好きになるのはこの先で、ただ問題提起をするだけではなく、すべてを肯定的に繋げて希望ある未来へと話を持っていくところだと思う。
最後は圧倒的に明るく、優しい気持ちで朱里たちを見送り、自分の人生を前向きに捉えているわたしがいた。