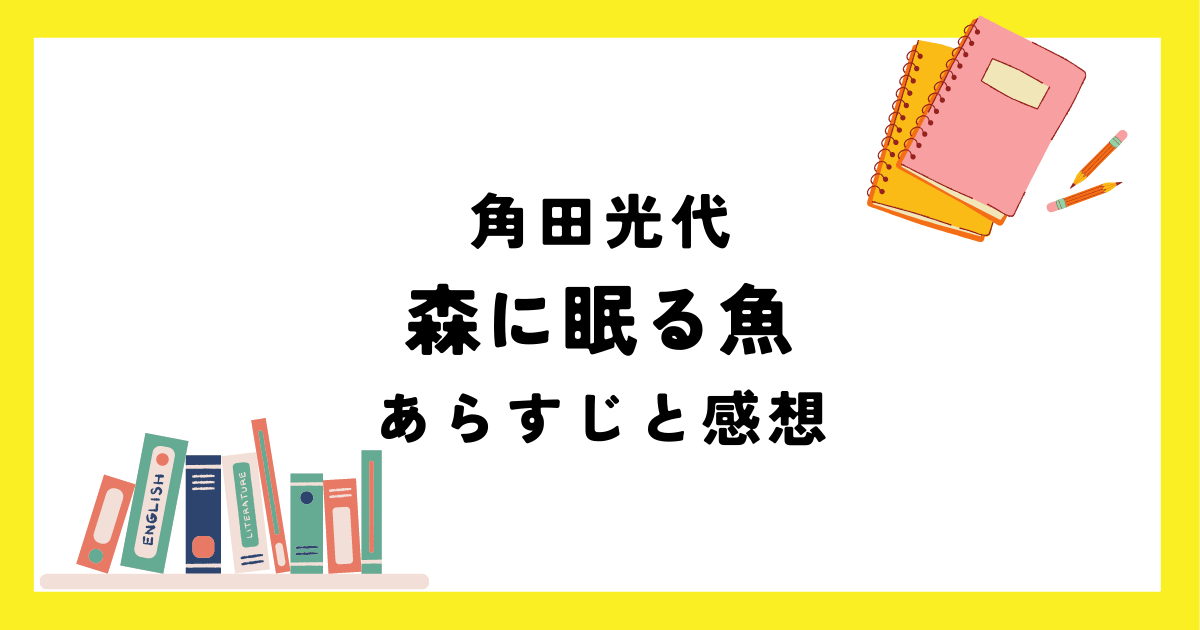あらすじ
東京の文京区で出会った5人の母親は、育児を通して心を通わせていくが、子供たちの小学受験を機にその関係が変化していく…。
5人の母親たちの共通点は同じ幼稚園に通う子供を持つこと。
きっと学生時代であれば仲良くならなかったであろうママ友は「子育て」を通し、信頼しあい学生の友人たちよりも多くの時間を共に過ごし、時に戦友のようにお互いを励ましあってきた。
しかし、「小学受験」をきっかけにお互いの育ってきた環境の価値観や家庭事情が明るみになる。
当初は小学受験に力をいれる母親たちに対し、ブランドもののバッグを見せびらかすのと一緒だと嫌悪を抱いていたが、気がつけば自分たちの見栄や夢を子供に託し、のびのび自由に育てたいと理想にしていた子育てからは遠く離れていく。
小学受験対策の「幼児教室」に通う母親たちは、友人だと思っているのについ自分の子どもと人の子どもを比べては落ち込んだり、安堵する自分に自己嫌悪する。
日常に振り回されながら現代に生きる彼女らの深い孤独と狂気の物語。
感想
子どもの時に絶対的存在だった母親もひとりの人間なんだと当たり前のことを思う。
子育てに良かれと思ってやってみたことでも上手くいかないこともある。
長年生きていても「お母さん」は、はじめてなのだから。
小説は「ママ友」を中心に話が展開されているが、女性だけの閉鎖空間に身を寄せ合っていると起こり得る出来事のように感じた。
みなそれぞれどこか変わった一部分を持ち合わせていて、5人が集まると巨大な違和感となる。
しかし、一度その輪の中に入ると不自然なことに気づくことはできない。
歳を重ねるに連れて、学生時代のように純粋にビビッドな感情だけで気の合う仲間を見つけることは難しくなってくる。
自分が何者かであるために繋がりを求めてコミュニティに依存してしまうのは母親だけでなく、誰もが一度は感じた経験があると思う。
「ママ友」のコミュニティの中で自分の立場を確立するために、子どもと自分を追い詰め破滅してしまっては、あまりにも悲しい。最後に残るのは、虚しさとやるせなさだけ。
人間の見たくない部分に出くわしてしまった時、傷つかないように生きるのではなく、簡単に傷つかない心(鈍感になる)を成長させておくことが必要なのかもしれない。
自分と大事な人を守るために。
それぞれの夫婦の在り方も様々で、日常的に「会話ができる」家族は素敵だなと思いました。